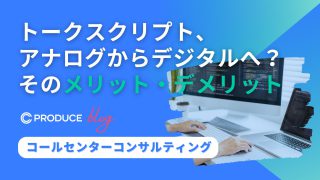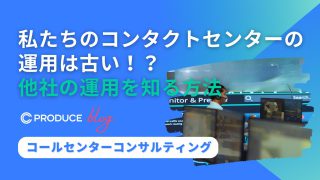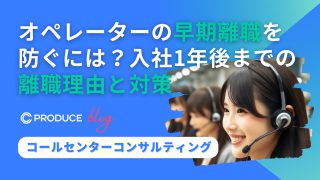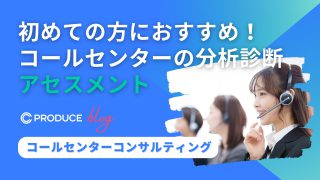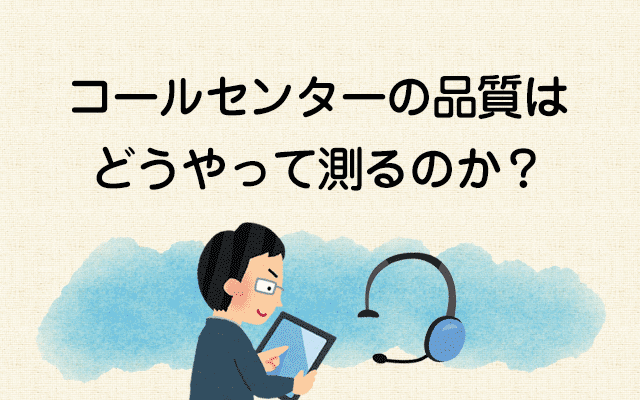
【コールセンターの品質はどうやって測るのか?1】はじめに
こんにちは、コールセンターコンサルティングのCプロデュース 代表取締役 大木伸之です。
このブログでは、コールセンター情報や日々の出来事などをご紹介しています。
コールセンターのメジャーメント
今から15年くらい前に、「メジャーメント」という言葉を意識するようになりました。
ご存じの通り、測定や測量の意味ですが、当時、ヨーロッパ(イギリス、スウェーデン)のコールセンターを視察する機会があり、その際に現地のアウトソーシング企業の運用チームがその言葉をやたらに使っていたのを覚えています。彼らは、コールセンターをどのように活用したら、その企業(クライアント)の利益に貢献できるかを、真剣に議論していたようです。
その中に生活消費財の企業のコールセンターがありました。そこではテレコミュニケーター自身が不良品の交換、返金などの判断をしていました。例えば「紙おむつが破けていた」といった顧客(乳幼児を持つ母親)からの入電には、迅速な対応が求められます。現地のマネージャーに聞くと、決められた質問に対する顧客の回答に問題がなく、日本円で2,000 円から3,000 円程度のことであれば、SV や上司の許可を得ずとも、運用ルールに従って、テレコミュニケーター自身の判断でクロージングしていくのだといっていました。
オペレーションの運用ルールなどは、転送やエスカレーションで顧客が時間的なロスを被らないように配慮して設計されていました。
KPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)
近年、日本のコールセンターにもたくさんの物差し(管理指標)ができており、応対品質の測定方法も多様化しています。KPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)という言葉もコールセンターに浸透してきています。しかしながら、それらを使った応対品質の改善活動が、最終的に企業の利益に結び付いているかは少々疑問が残ります。
次回、【コールセンターの品質はどうやって測るのか?2】応対品質の重要性 へ つづく・・・
date :
記事を書いた人
大手企業、中小企業のコールセンターを運営している事業会社に対して「改善コンサルティング」「コールセンターの協業運営」サービスの提供を行い、コールセンター業界の最前線を見てきた。精通する業界はISP、通信販売、保険、クレジットと多岐にわたる。コールセンターのビジネスにおいて、”オペレーションの現場”と”経営層”までの距離をいかにコンパクトにできるかが成功への鍵であるとの持論から、実践型のコンサルティングを推進している。
お気軽にお問い合わせください!
リモートワーク中につき、代表電話が繋がりにくい場合がございます。その場合、恐れ入りますが、お問い合わせフォームまたは、直接担当者の携帯電話(メール)にてご連絡くださいますようお願い申し上げます。
お気軽にお問い合わせください!
リモートワーク中につき、代表電話が繋がりにくい場合がございます。その場合、恐れ入りますが、お問い合わせフォームまたは、直接担当者の携帯電話(メール)にてご連絡くださいますようお願い申し上げます。